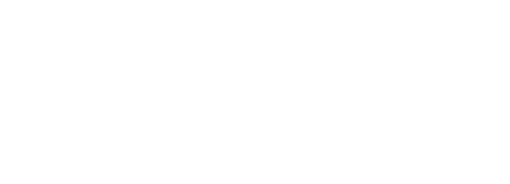2025年1月12日から14日に、日本緑化工学会の現地検討会が開催されました。能登学舎から中村が参加し、現地案内の一部を担当致しました。
いくつかの応急仮設住宅を見学させて頂きました。金沢工業大学建築学部の手代木さんから、自治体ごとに、住宅の仕様が様々あること、入居者の配置への工夫、そもそも立地に制限のある中、施設配置などで様々な工夫があったことなどが説明されました(写真1,2)。石川県では、従来よく見られるプレハブ型に加えて、木造、ユニットハウス、トレーラーハウスなどが利用されています。木造の仮設住宅については、熊本地震をモデルにした「まちづくり型」と、みなし仮設住宅で生活する方が地元に戻る「ふるさと回帰型」が整備されています。写真-2は元々公園であったところに設置された住宅です。このように公園やオープンスペースに整備された住宅が使用され続ける場合、住宅地としての転用となる可能性があります。将来のビジョンや再整備を視野に入れた検討、柔軟な対応が望まれます。


現地検討会では能登半島で進められてきた取り組みや、地震や奥能登豪雨による影響を見学しました。写真-3は石川県立大学の上野さんにご案内頂いた、輪島市町野町東区、トキ生育環境整備のモデル事業地です。町野川流域では地震による崖崩れなどが多数発生、その後の奥能登豪雨でも多くの土砂が流出しました。町野川河口では堆積した土砂により河口の流れが変わり、生き物へ影響があることが報告されています(写真-4)。


石川県奥能登農林総合事務所では、森林部の中榮様から地震や豪雨に対する取り組みを、また、企画調整室/いしかわ農業総合支援機構の細川様からトキの放鳥に向けた取り組みを伺いました(写真-5)。日本緑化工学会では、自然環境に配慮すべき地域を中心に、地域性種苗(ある地域内から採取、育成した種苗)の活用を進めています。地域の種を地域で生産し、地域の業者が地域の緑化工事を実施することを目指した活動について、能登における将来の可能性や方向性について意見交換を行いました(写真-6)。


能登半島では復興に向け、また持続的な地域経済の構築に向け、今後も様々な取り組みが進められていくことと考えられます。各地域の実情を伺いながら、可能なところでご一緒できるようにしていきたいと考えています。 今回ご一緒頂いた学会員の皆様、ご案内頂いた皆様、ありがとうございます。また様々な議論ができることを楽しみにしております。
(文責 金沢大学 中村華子)