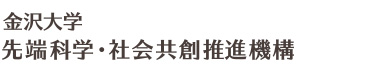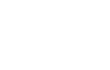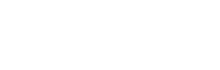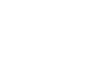1.創薬関係のベンチャーは可能か?
1、新薬開発の経費
テレビのコマーシャルで小野薬品でしたか「最近の新薬開発の成功率は0.03%」と言うのを見た人もいると思います。昔千三つ、今万三つです。1万の候補物質から3つが薬になるという確率です。 新薬の開発経費はそのような候補物質を化学合成したり、天然物から見つけ出したりする段階(①)と、それらは玉石混交ですから、役立つものを選り分ける段階(②)、そして、その選り分けた最終候補物質をヒトに安全に投与でき、しかも効果が確実かどうか、即ち、医薬品としての評価を行う段階(③)に入ります。それで御終いではありません。薬として商業生産する研究(④)の4段階に大別できます。 経費は、4段階合計で、約1,000億円と言われています。では、ベンチャー企業創設は無謀か? 否、そんな事はありません。
2、新薬開発のための諸研究
段階① 候補物質の創出または発見:
様々な有機合成、無機合成、植物・動物など生物の成分抽出とその構造研究が為されています。大学理学部、薬学部、化学工学など大学研究室の得意分野です。ファイザーのような大きな製薬企業では従来の低分子物質から生物由来の高分子物質へと変わってきています。
段階② スクリーニング:
沢山の候補物質から薬の有望候補を見つける作業はスクリーニングと呼ばれます。段階①で山のように物質が作られたり、見つかったりしますが、薬として有用かどうか調べなければなりません。それを調べる上で重要な事は、薬用量と中毒する量との比率です。大学の研究はこの比率を無視して先に進む事が多く、結果として、試験管の中で効果が認められただけでヒトに投与できる薬にはならないのです。 実際には、段階①と②は明確に分かれるものでは無く、スクリーニングの結果、更に有望な物質が想定されれば、段階①のような研究が為されます。 いよいよ候補物質が絞られれば、段階③になりますが、もうこの時点では、簡単に候補物質を変更できません。次の各種試験を行わなくてはならず、候補物質を変更すれば一からやり直しになるからです。
段階③ 医薬品としての評価:
次に示すように様々な試験が必要になります。投与経路が注射によるものですと、厳しい検査基準が適用されます。
前臨床
動物実験:
各種毒性試験(急性毒性試験、亜急性毒性試験、慢性毒性試験、発がん性試験、催奇形性試験、遺伝毒性試験、抗原性試験、皮膚毒性試験など)、
薬効薬理試験
一般薬理試験
吸収代謝排泄試験など
製剤化研究(ヒトに投与する剤型を研究します。) 薬物の安定性研究(何度で何時まで安定か、光で分解されるか、分解物はなにかなど)
臨床試験
Phase Ⅰ、Phase Ⅱ、Phase Ⅲ、市販後調査など
段階④ (一部は段階③の途中から始めます)
医薬品開発には多額の費用が掛かりますので、製薬企業は商業生産をして、その費用を回収すると共に利益を上げて次の医薬品を開発しなければなりません。商業生産をするためには下記の事柄を達成し、製造承認を取得する必要があります。今では、世界中に売れなければ元が取れませんので、世界各国の製造承認を取る必要があります。
・各国の定めるGMP(Good Manufacturing Practice)製造確立.
・スケールアップ製法確立(試験管で出来ても駄目で、世界中の需要に応えれられるよう、例えば、タンクでの製法を確立する必要があります。)
・規格確定(毎回同じ品質の製品が出来ていることを確認しなければなりません。なお、新薬では、分析方法そのものも研究して確立する必要があります。)
・プラント建設(注射用医薬品製造では、医薬品は勿論、無菌の空気、水の製造も重要)
・品質管理組織構築
・品質保証組織構築
・当局の査察対応 等
3、ベンチャーの可能性は何方でも大
このように、実に沢山の研究・開発が必要です。そこにベンチャーを立ち上げる可能性があるのです。その範囲は、上の項目から明らかな如く、薬学部に限らず。理学、工学、医学、法学、経済学など沢山の分野に跨ります。
経済産業省は今これまでの原発政策からライフサイエンス支援政策に大きく舵を切っているように感じられます。私はチャンス到来と思っています、
次回から多岐に亘る開発の各論のお話を記載します。参考にして下さい。